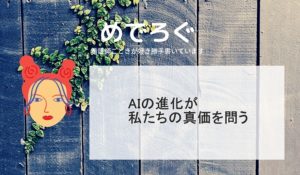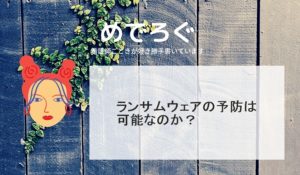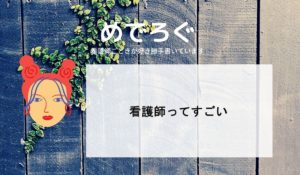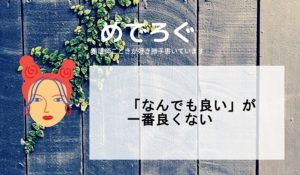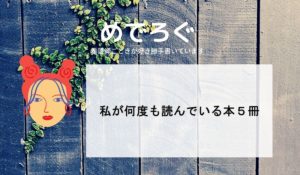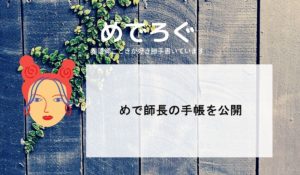師長(所属長)になって、年に2回スタッフ面接を行っている。
上期と下期に1度ずつ。
具体的には4月と9月に実施している。
どこの病院も同じころに面接を行っていると思うが、この「面接」は効果的なモノにしなければならない。
特に部署を変わって「初めて」スタッフと関わるときは目的を持って行う必要がある。
スタッフも師長も「お互い」の事を知らない状態で話さなければならない。
スタッフが「何を大事にしているのか」「何を考えているのか」「どんな不満を感じているのか」「何を目標としているのか」・・・など。
そして、師長はどのようにサポートすることができるかを考えるきっかけになる。
なので、面接の前に「面接準備シート」を渡して書いてもらう。
①上期(または下期)の自己評価
②病棟・病院改善に向けて、日頃から工夫や努力していること
③病院における自分の役割の達成具合は100点中何点くらいですか?
もし、100%でなかったら、今後どんな努力が必要ですか?
④病院の発展や自分自身の成長のために、周りのスタッフや病院にリクエストしたいことがあるとしたら何ですか?
の4つを事前に書いてもらい、面接に臨んでもらう。
普通に「面接します」となると、普通は「悪いところを指摘される」と考える人が多い。
面接はスタッフの弱点を指摘してモチベーションを下げる場所ではない。
ましてや師長の鬱憤を晴らす場所でもない。
面接を効果的に行うためには、仕事に対する「考え方」を擦り合わせないといけない。
スタッフが「自分にできること」を知ってもらう。
「弱みを克服」するのではなく、「強みを活かせる」ように仕向ける。
管理者(師長)は「ストレングスファインダー」という考え方を用いた方が良い。
ドラッカーも言っているが、「弱みを克服する事に時間を使うより、得意なことを伸ばす事に時間をつかうべきだ」と話している。
「弱みの克服」は時間がかかる割に効果的ではない事が知られている。
つまり、効率が悪いのだ。
スタッフを「一律に」育てる必要はない。
「患者さんと話す」事が得意な人もいれば「知識を使ってアセスメント」を得意とする人もいる。
知識はある一定の「基準」さえあれば何とかなる。
「気が利く」とか「仕事のスピード」とか、管理者になるとつい求めてしまいたくなるが、言い出すとキリがない。
この考え方を捨てないと、結局「欠点」ばかりに目が行く。
「あの人は患者さんに優しいけど、知識がない」
「あの人は知識ばかりあって、動こうとしない」
「あの人は患者さんと話ばかりして、仕事がさばけない」
など
「管理者都合」の目線が入る。
そして、これは「仕事だから」という言葉で簡単に「正当化」できる。
完璧な人間なんていないはずなのに、「完璧な人間作り」に注力しようとする。
「できない」ものは「できない」と割り切る場面も必要であるし、「できない(苦手)」な事にあまり力を使うことは、効率が悪い。
その考え方を変えると、組織が変わる。
得意な事をお互いに活かし、思い切った仕事ができる。
結果的に、自尊心が向上し、仕事に対するモチベーションが上がる。
たかが「面接」であるが、されど「面接」である。
わざわざ時間を作ってやるのなら、その後に影響力をもたらす時間にしたいものだ。