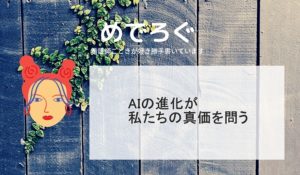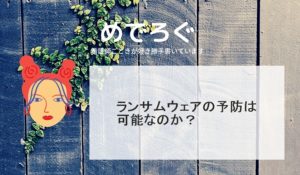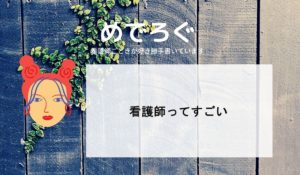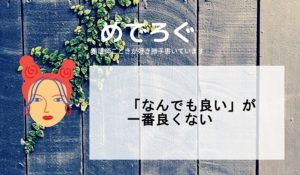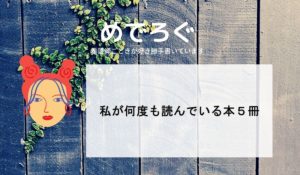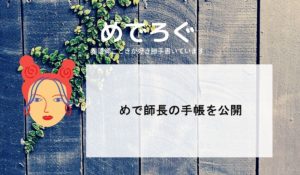夜中の1時ころ、ある精神科病院から転院依頼の電話がかかってきた。
主訴は「意識障害」と「ショック」
第一報を聞いたとき、突然の状態悪化(急変)かと思っていたが、よくよく話を聞くと・・・
- 1ヶ月前くらいから殆ど食事が取れていない
- 1ヶ月で10kg体重が減った
- 夕方まで声を出していたが、声を出さなくなった
- 血圧を測定したら60台だった
こんなに悪くなるまで放置していたのか?
病院に入院していながら、「食事が摂れていない」と把握しておきながら、ここまで悪くなるのを待っていたのか?
患者の体重は25kg(元々は45kgくらいあったらしい)
フォーリーカテーテルを挿入すると、薄茶色の膿の様な液体が出てきた。
おそらく、殆ど水分も摂れていない。
そもそも、こういう症例は夜間(深夜)帯に運び込む症例ではない。
もっと早く、昼間に転院調整を行うべき症例ではないのか?
これが日本の医療の現状か・・・と辟易してしまう。
精神科病院への偏見を持ってはいけないと思うが、時々このような症例は運ばれてくる。
私も精神科病棟の経験があるが、「身体疾患」に対しての意識が弱すぎる。
ICUの経験もあるので、「これが同じナースなのか?」「これで同じ給料なのか?」と疑問を感じたこともある。
精神科スタッフは精神を「落ち着かせれば良い」「大人しくなれば良い」というものではない。
普段の業務は日常生活援助が中心となるかもしれないが、きちんと「身体症状」も見逃さないようにアセスメントしなければならない。
看護師も医者も医療を学んできたプロである。
患者の訴えだけを信じるのではなく、自分の頭で考えてアセスメントするべきであろう。
それができないなら「ただの素人」であり、「お医者さんごっこ」「看護師ごっこ」になる。
もう少し「考える」「疑う」という事をサボらずに行っては如何だろうか?
学生の頃は、課題が出され、嫌でも勉強する機会が与えられた。
社会人は「自分に必要なこと」を「自分で」学ぶ力が必要になる。
一人で学ぶのが難しければ、「このままで大丈夫でしょうか?」と疑問を投げかけるくらいはできるはずである。
疑問を「声」に出せば、誰かが知っている事を話してくれるかもしれない。
先日「声」について記事を書いたが、やはり「声」は何かを変えてくれる。
皆で「見て見ぬ振り」しない文化は作っておきたいものである。