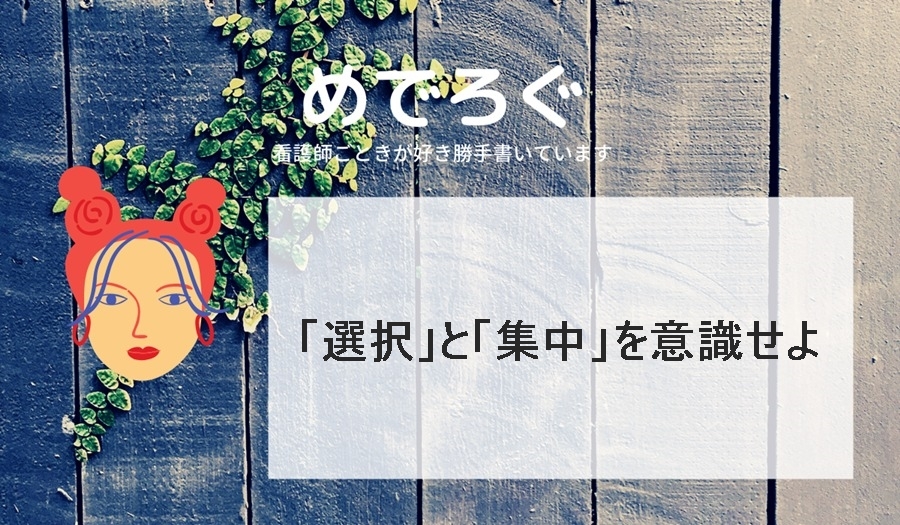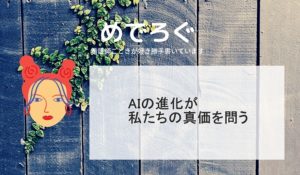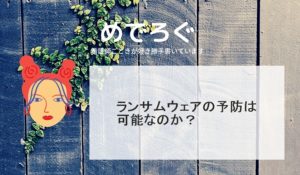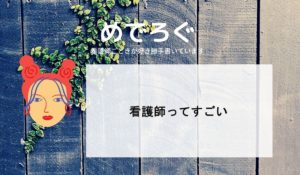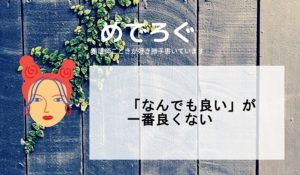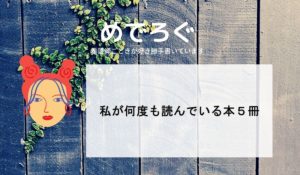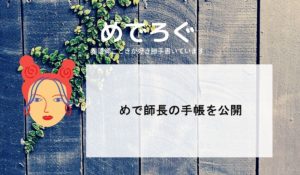「『良いこと』を何でも取り入れる」
こういう思考の人は結局何も達成できない。
看護の世界にいると、「患者さんのために」という意識が強く、
「良い」と考えられる事を、何でもかんでも取り入れようとする傾向にある。
それは「良いこと」かもしれないが、最終的に成果が出ているのか・・・
全体を俯瞰して判断することが必要である。
それで、スタッフが疲弊していないだろうか?という視点も大事である。
何を大切にするかは組織によって変わってくるかもしれない。
もしくは、管理者の考え方によっても変わってくるだろう。
「師長が何にこだわっているか」という部分は、病棟の文化に影響を与える。
私は「患者第一」とは思っていない。
こんな事を書くと、「医療者として失格」などという批判を受けるかもしれないが、何でも「患者第一」にはできない。
どちらかというと、「スタッフ第一」という思考が強い。
スタッフが健康であり、働きがいを持ち、笑顔でいないと、患者ケアの質は上がらない。
「患者のため」という言葉でスタッフを押さえつけて
仕事を「やらせよう」とすると、モチベーションは上がらず、
最終的には患者のためにならない。
このブログでも何度も書いているかもしれないが、「やらされ感」では人は成長しない。
管理者として、何を取り入れ、何をやらないか・・・を決める必要がある。
コンサルタントの読書術(大石 啓之 署)という本の中にはこうある。
日本人は選択と集中が苦手であり、切り捨てるということがなかなかできない。
あれも大事、これも大事というように、何でも取り入れようとするあまり、1つ1つの掘り下げが浅くなって、結局なにも行動に結びつきません。
何もかもやろうとすると、結局何もできないのだ。
何をやらないか・・・という視点も大事である。
勉強も同じ。
心電図の勉強も、薬の勉強も、検査の勉強も・・・とやっていると、永遠に何も達成できない。
病棟にいる入院患者の特色を捉え、
「心電図ならここまでの知識」
「薬は、よく使っているこの薬の事は押さえておこう」
「検査はこの部分は見落とせない」
など
何もかもやるのではなく、ポイントだけやるべきである。
私は病棟内で定期的に「テスト」を行っている。
病棟内で必要な知識のテストである。
テストで満点を取って欲しいのではない。
もちろん、答えも公開する。
「ここまで知っておいて欲しい」という病棟内での「基準」を示している。
育休明けのスタッフもその「テスト」を事前に復習しておけば安心だと話す。
『基準』を明確にすれば、スタッフの会話の中に「共通言語」が生まれる。
患者の容体が良くなっているか、悪くなっているか、よく話すようになる。
何を知っておくか『選択』して、『集中』して勉強すれば良い。
そうすれば、短期間で成果が出る。