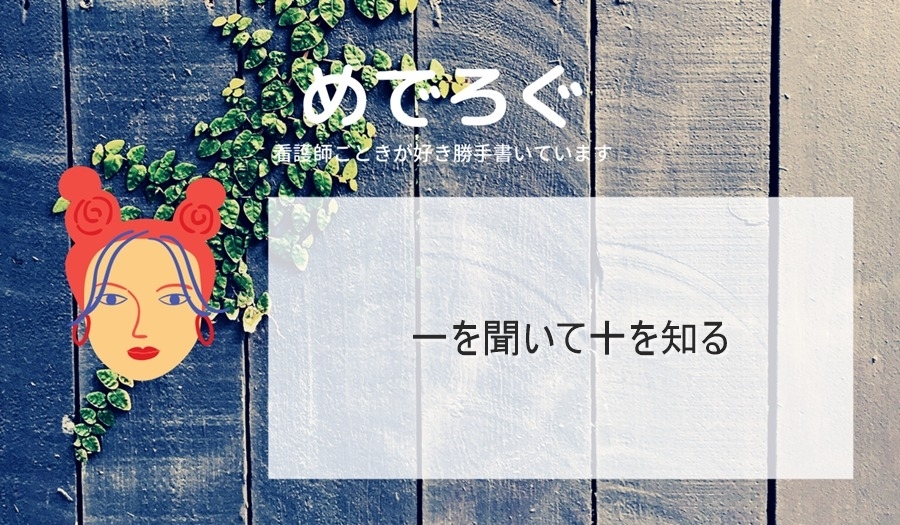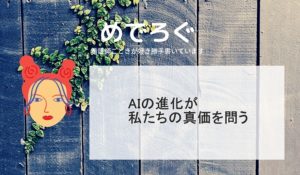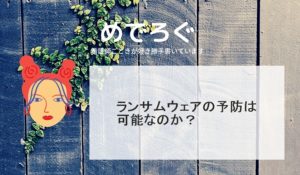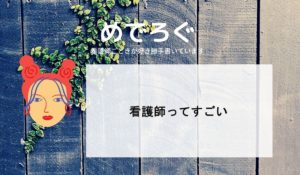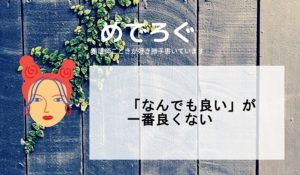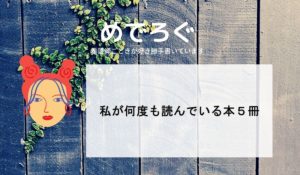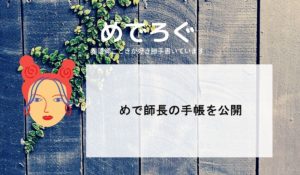『一を聞いて十を知る』という格言をご存じだろうか?
聞いたことのある人も多いだろう。
一を聞いて理解出来る人と出来ない人の『差』は何だろう?
- 最近の若者は気が利かない
- 段取りが悪い
- 口ばかりで動かない
- すぐに動こうとしない
- 教えてもらっても感謝しない
など、いわゆる「使えない人材」の話をよく耳にする。
一方若者は若者で、「言われないとわからない」「言われた事をやったのに怒られた」と思っているかもしれない。
Twitterでも「言われないとわからない」というつぶやきを目にする。
私はこの「使える人材」と「使えない人材」の差は『想像力』だと思っている。
相手が何を求めているのかを知り、先取りで動けるかどうかだ。
先輩が「~してきて」と言ったとき、「先輩はどうしてそれが必要だと思ったのか」を想像できるかどうかだ。
看護の世界で言えば、「輸液ポンプ取ってきて」と言われた時、先にベッドサイドに『点柱台(点滴台)』があるか無いか、『差し込む電源先は空きがあるか』を瞬時に確認し、輸液ポンプとコードを準備する。
この確認を行わないと、二度手間になる。
ただ言われるがまま、「輸液ポンプ」の機械だけを持ってくるような看護師は「子供の使い」である。
(要領を得ない、あまり役に立たない使いの意)
「ガキの使いじゃあるまいし・・」と揶揄するような言葉は昔からある。
要するに、「おまえは気が利かないバカか」という意味である。
この想像力は訓練で鍛えることが出来るが、ある本に「子供の頃のお手伝い」が有効だと書いてあった。
お手伝いは親から家庭の仕事の一部を任される。
その課程で、コミュニケーション力、段取り力、計画力、問題解決力、最後までやり遂げる力などが身につくという。
たったひとつの行動の中に色んな「力」が隠れている。
企業によっては「小さい頃に親の手伝いをやったことが無い人」は採用しない企業もあるそうだ。
医療の世界は「人間」を対象とするサービスである。
「相手が何を求めているのか」を想像できる人が必要である。
そして、この力は後天的な力であり、身につけることができる。
今から想像する訓練をやってみよう。
きっと世界が変わるはずである。